特定技能で家族帯同や永住はできる?1号・2号の違いと現実的な選択肢
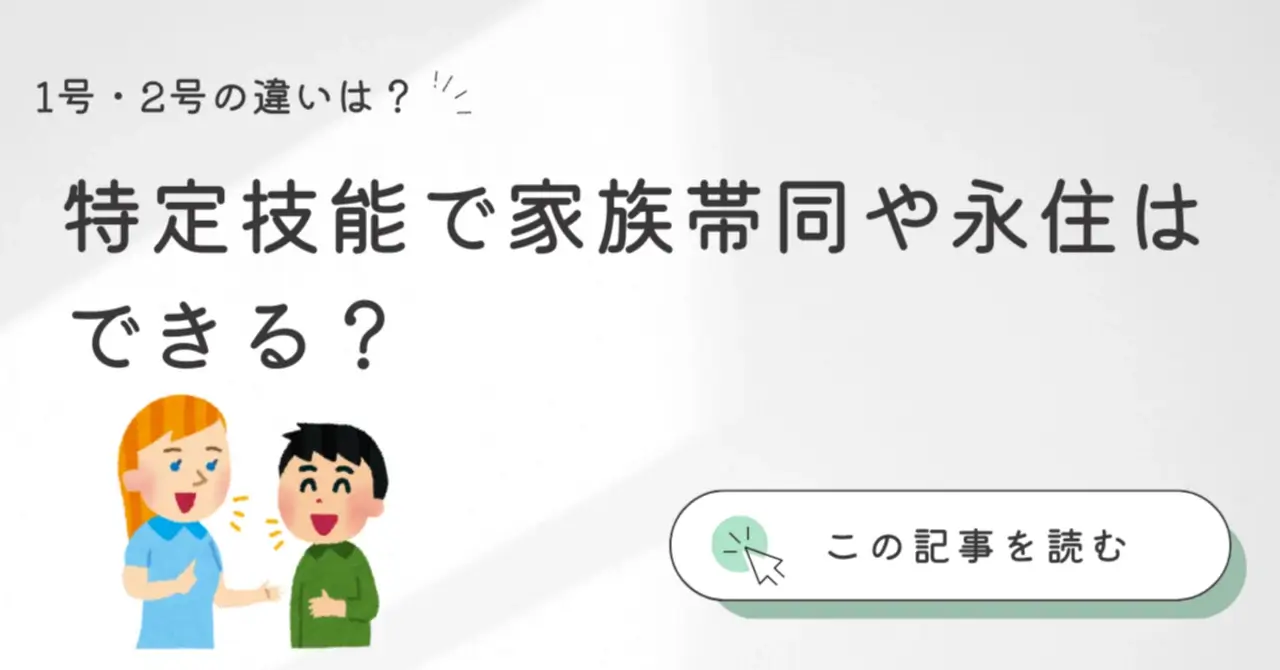
医療介護ネットワークのコラムにご訪問いただき、ありがとうございます。
人手不足への対応策として特定技能外国人の採用を検討する中で、
「採用した外国人の家族帯同は認められているのか」
「将来的に永住を希望された場合、どう説明すればよいのか」
といった点に悩む採用担当者も多いのではないでしょうか。
制度を正しく理解しないまま採用を進めてしまうと、本人との認識のズレや、将来に関するミスマッチにつながることも。
そこで本記事では、「特定技能 家族 帯同」「特定技能 永住」というテーマについて、雇用する側が押さえておくべき制度の結論と注意点を整理。
特定技能1号・2号の違い、そして企業として説明しておきたい現実的な選択肢を分かりやすく解説していきます。
特定技能で家族帯同や永住はできるのか?まず結論を整理

特定技能外国人の採用を検討する際、家族帯同や永住の可否は、後からトラブルになりやすい重要なポイントです。
まずは制度の結論を整理し、採用前に企業として説明すべき前提を押さえておきましょう🌿
特定技能1号では家族帯同・永住はできない
特定技能1号は、介護などの人手不足分野で即戦力として働いてもらうことを目的とした在留資格です。
そのため、原則として家族帯同は認められておらず、永住申請の対象にもなりません。
現場では「長く働けば家族も呼べるのでは」「何年いれば永住できるのでは」といった期待を持たれることもありますが、制度上はそうした前提は置かれていないので注意しましょう。
採用時点でこの点を曖昧にしてしまうと、後々の認識のズレにつながるため、企業側が正確に説明しておくことが大切です。
なお、特定技能1号では原則として家族帯同は認められていませんが、人道上の配慮など、極めて限定的な事情がある場合に例外的に許可されるケースがあるとされています。
ただし、これはあくまで例外的な対応であり、一般的なケースではありません。
採用の際には期待を持たせる表現は避け、制度上は原則認められていないという点を軸に説明することが望ましいでしょう。
特定技能2号なら家族帯同・永住の可能性が出てくる
一方で、特定技能2号は、熟練した技能を持つ人材が長期的に日本で働くことを想定した在留資格です。
この2号に移行できた場合、配偶者や子どもの家族帯同が可能となり、将来的には永住申請を検討できる立場になります。
ただし、2号に移行したからといって自動的に永住できるわけではなく、在留年数や収入、納税状況など、別途審査が行われます。
企業としては、「2号になればすべて解決する」という誤解を与えないよう、位置づけを正しく伝えることが重要です。
特定技能2号で家族帯同が認められる範囲は、配偶者と子どもに限られています。
両親や兄弟姉妹など、その他の親族を呼び寄せることは認められていないため、企業としてもこの点を正確に理解し、説明できるようにしておく必要があります。
特定技能1号と2号の違いとは?家族帯同・永住の可否が分かれる理由

家族帯同や永住の可否が、なぜ特定技能1号と2号で大きく分かれるのか。
その背景には、それぞれの在留資格が想定している「働き方」と「滞在の位置づけ」の違いがあります🔎
制度の考え方を理解しておくことで、採用後の説明や判断がしやすくなります。
ここでは、家族帯同や永住の可否が分かれる理由を見ていきましょう。
特定技能1号は人手不足を補うための在留資格
特定技能1号は、深刻な人手不足が続く分野において、一定の技能と日本語能力を持つ即戦力人材を受け入れることを目的とした制度。
在留期間には上限があり、更新を重ねながら働くことはできるものの、制度設計上は「一時的な就労」を前提としています。
そのため、生活基盤を日本に完全に置くことや、家族とともに暮らすことまでは想定されていません。
企業側としても、長期雇用を前提にしすぎず、制度の枠内でどのように戦力化・定着を図るかを考える必要があります。
特定技能2号は長期就労を前提とした在留資格
これに対して特定技能2号は、より高い熟練技能を持つ人材が、長期にわたって日本で働くことを前提とした在留資格です。
在留期間の更新に上限がなく、安定した就労が見込まれる点が大きな特徴。
この「長期就労を前提とする」という考え方があるからこそ、配偶者や子どもの家族帯同が認められ、永住申請への道も開かれています。
企業にとっては、将来的に中核人材として育成する選択肢が生まれる資格だといえるでしょう。
特定技能2号に移行できる分野が限られている現実
注意しておきたいのは、特定技能2号に移行できる分野が、建設や造船・舶用工業など一部に限られているという点です。
すべての業種で2号を目指せるわけではなく、制度上の制約があります。
そのため、採用時点で「将来は2号に移行できるか」「そもそも自社の業種が対象か」を把握しておかないと、本人の期待と制度の現実にギャップが生じてしまうことも。
分野ごとの制度内容を理解したうえで、将来像を共有することが、無用なトラブルを防ぐポイントになります。
また、特定技能2号へ移行するためには、分野ごとに定められた技能検定の上位レベルや、一定の実務経験が求められます。
単に在留期間を重ねればよいわけではなく、技能水準の証明が必要となるため、企業側も「誰をどのように育成するのか」を中長期で考える視点が欠かせません。
特定技能から家族帯同・永住を目指すための現実的な選択肢

特定技能外国人を採用する企業にとって、「この人材とどのくらいの期間、一緒に働けるのか」「将来の希望にどう向き合うべきか」は重要な検討事項です。
制度の制約を踏まえたうえで、現実的に考えられる選択肢を整理しておくことで、採用後のミスマッチを防ぎやすくなります。
ここでは特定技能の制度を踏まえたうえで、家族帯同や永住を見据える場合に考えられる現実的な選択肢を整理していきます。
特定技能2号への移行を目指すという考え方
将来的に家族帯同や永住の可能性を視野に入れる場合、まず考えられるのが特定技能2号への移行です。
ただし、2号は誰でも簡単に移行できるわけではなく、対象分野や技能水準といった条件があります。
企業側としては、本人のキャリア形成を意識しながら、長期的に育成できる環境があるか、2号を目指す現実性があるかを冷静に判断することが求められます。
早い段階で将来像を共有しておくことが、双方にとって納得感のある雇用につながります。
特定技能以外の在留資格へ変更するという選択
もう一つの選択肢として、特定技能から別の在留資格へ変更するルートも考えられます。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」などは、職種や学歴、業務内容によっては検討の余地があります。
この場合、単に在留資格を変えればよいという話ではなく、業務内容が資格要件に合致しているか、企業側の体制が整っているかがとても重要。
特定技能の採用をきっかけに、その後のキャリアをどう設計するかは、企業の受け入れ姿勢にも大きく左右されます。
永住申請を見据えた生活・就労の整え方
永住申請を見据える場合、在留資格の種類だけでなく、日々の就労状況や生活の安定性が重要な判断材料になります。
永住の審査では、長く安定して日本で働いているか、収入や納税に問題がないか、生活態度に大きな問題がないかなどが確認されます。
これらを把握しておくと、本人から将来の相談があった場合にも落ち着いて説明できるようになるので、しっかり覚えておきましょう。
永住申請では、原則として「10年以上日本に継続して在留していること」や「就労資格での在留期間が一定以上あること」が求められます。
ここで注意したいのが、特定技能1号での在留期間は、永住申請における就労資格の在留期間としてはカウントされないという点です。
一方、特定技能2号や他の就労系在留資格での在留期間は、永住申請の要件に含まれるため、長期的な雇用が継続できれば条件を満たしやすくなります。
ただし、介護分野の特定技能には現在2号が設けられていないため、介護分野で働く外国人材が永住を目指す場合は、別のルートを視野に入れる必要があります。
代表的な選択肢として挙げられるのが、介護福祉士の資格を取得し、「介護」の在留資格へ変更するルート。
特定技能は、日本で働き始めるための入口となる在留資格であり、それ自体が永住を前提とした制度ではありません。
永住を視野に入れる場合は、その先の資格取得や在留資格の変更も含めて、段階的にキャリアを考えていくことが現実的といえるでしょう。
【まとめ】特定技能で家族帯同・永住を考えるときに押さえておきたいこと
特定技能外国人の採用では、家族帯同や永住に関する制度理解が欠かせません。
あらかじめ前提を整理しておくことで、採用後の認識のズレや将来のトラブルを防ぎやすくなります。
-
特定技能1号のままでは、原則として家族帯同や永住は認められていない
-
特定技能2号に進むことで、家族帯同や永住申請が視野に入る
-
ただし、2号への移行には分野や技能水準などの条件があり、すべてのケースに当てはまるわけではない
なお、介護分野の特定技能には2号が設けられていないため、家族帯同や永住を見据える場合は、介護福祉士の資格取得や在留資格変更を前提とした中長期的なキャリア設計が重要になります。
特定技能は人手確保の手段であると同時に、その先をどう設計するかで成果が大きく変わる制度であることを、企業側も意識しておきたいところですね。